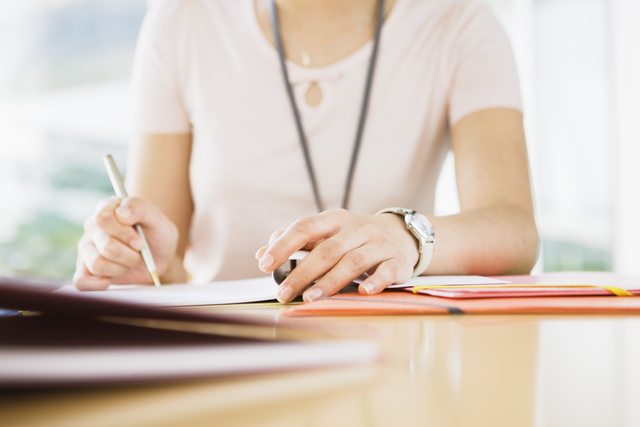相続無料相談受付中!
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
06-6770-5769
相続分について
法定相続分
| 配偶者相続分 | 子(第1順位) | 直系尊属(第2順位) | 兄弟姉妹(第3順位) |
| 1/2 | 1/2 | ───────── | ──────── |
| 2/3 | ──────── | 1/3 | ──────── |
| 3/4 | ──────── | ──────── | 1/4 |
同順位の血族相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分け合います。
たとえば、配偶者と子が3人いる場合、子の相続分である2分の1を3人で分けることになり、子はそれぞれ6分の1ずつ相続します。
兄弟姉妹が相続人である場合、半血(父母の一方のみが同じである)の兄弟姉妹がいる場合は全血の兄弟姉妹の2分の1の相続分となります。
代襲相続人の相続分は、被代襲者(もともと相続人となるべきであった者)の相続分と同じです。
指定相続分
被相続人が遺言で相続人の相続分を指定していた場合には、それに従うことになります。
特別受益者の相続分
共同相続人中に遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組、生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、他の共同相続人との公平を図るため、遺贈や贈与を受けた分(特別受益といいます)を計算上相続財産に戻して(これを持戻しといいます)、各相続人の相続分を算定する制度を特別受益者の相続分といいます。
特別受益に当たる行為かどうかについては、遺贈についてはすべて特別受益に当たるとされますが贈与は個別的に判断されることになります。
一般に婚姻や養子縁組に際して被相続人から渡される支度金とか持参金の名目で支払われるものは特別受益に当たると考えられますが、結納金や挙式費用については特別受益に当たるかどうかは争いがあります。
生計の資本としての贈与については、居住用や事業用不動産の贈与を受けたり、会社の運転資金の贈与、不動産の無償貸与など多岐にわたります。学費については、被相続人の社会的地位や資産状態などから判断して扶養義務の範囲を超えているとみられるものは特別受益に当たると考えられています。
特別受益の持戻し免除
特別受益がある場合でも、被相続人の意思表示により持戻しを免れることができます。
持戻し免除の意思表示は、黙示でもよいとされていますが、後日の争いを避けるため遺言書にその旨を記載しておくほうがよいでしょう。
ただし、持戻し免除の意思表示があっても他の相続人の遺留分を害することはできず、他の遺留分減殺請求権を行使することで、自己の遺留分は確保することができます。
寄与分制度
共同相続人中に被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付をしたり、被相続人の療養看護などにより被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした者は、法定相続分に寄与分を加えた財産の取得が認められます。これを寄与分といいます。
特別受益と同じく共同相続人間の公平を趣旨としていますが、寄与分のほうは寄与分として認められる分を相続財産から控除して各自の相続分を算定したのち、寄与者に寄与分を与えるというものです。
寄与分の有無や具体的な額については共同相続人の協議で定めますが、協議が整わないときは家庭裁判所に請求することができます。
なお、寄与分が認められるのは相続人のみです。相続人でない者には寄与分は認められません。
何が寄与行為に当たるかは個別具体的に検討する必要がありますが、少なくともその行為が被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をしたと判断できるものでなければなりません。
たとえば、被相続人の事業を手伝っていたが給料が払われていなかったり、民法の定める扶養義務や扶助義務などを超えて療養看護に努めたおかげで介護サービスの利用料負担を抑えることができた、などの事情があれば寄与分が認められる可能性があります。
二重資格者の相続分
ケース1
養子Aと実子Bが婚姻して夫婦になった場合、AとBは夫婦でかつ兄妹または姉弟という関係になります。
AB夫婦には子がおらず、直系尊属もすでに全員死亡し、ABの他に兄弟姉妹としてCがいるとしてAが死亡した場合、BはAの配偶者としての相続分は取得しますが、兄弟姉妹としての相続分は認められません。

ケース2
DE夫婦には子F、Gがおり、Fには子Hがいる場合に、Fが死亡し、DE夫婦が孫にあたるHを養子としたのちDが死亡した場合、Dの相続に関してHはDの養子でかつFの代襲相続人という関係になります。
この場合に、HがDの養子としての身分とFの代襲相続人としての身分で二重に相続分を取得できるかどうかについては争いがありますが、登記実務では二重資格を認めています。つまり、Hは2人分の相続分を取得することになります。